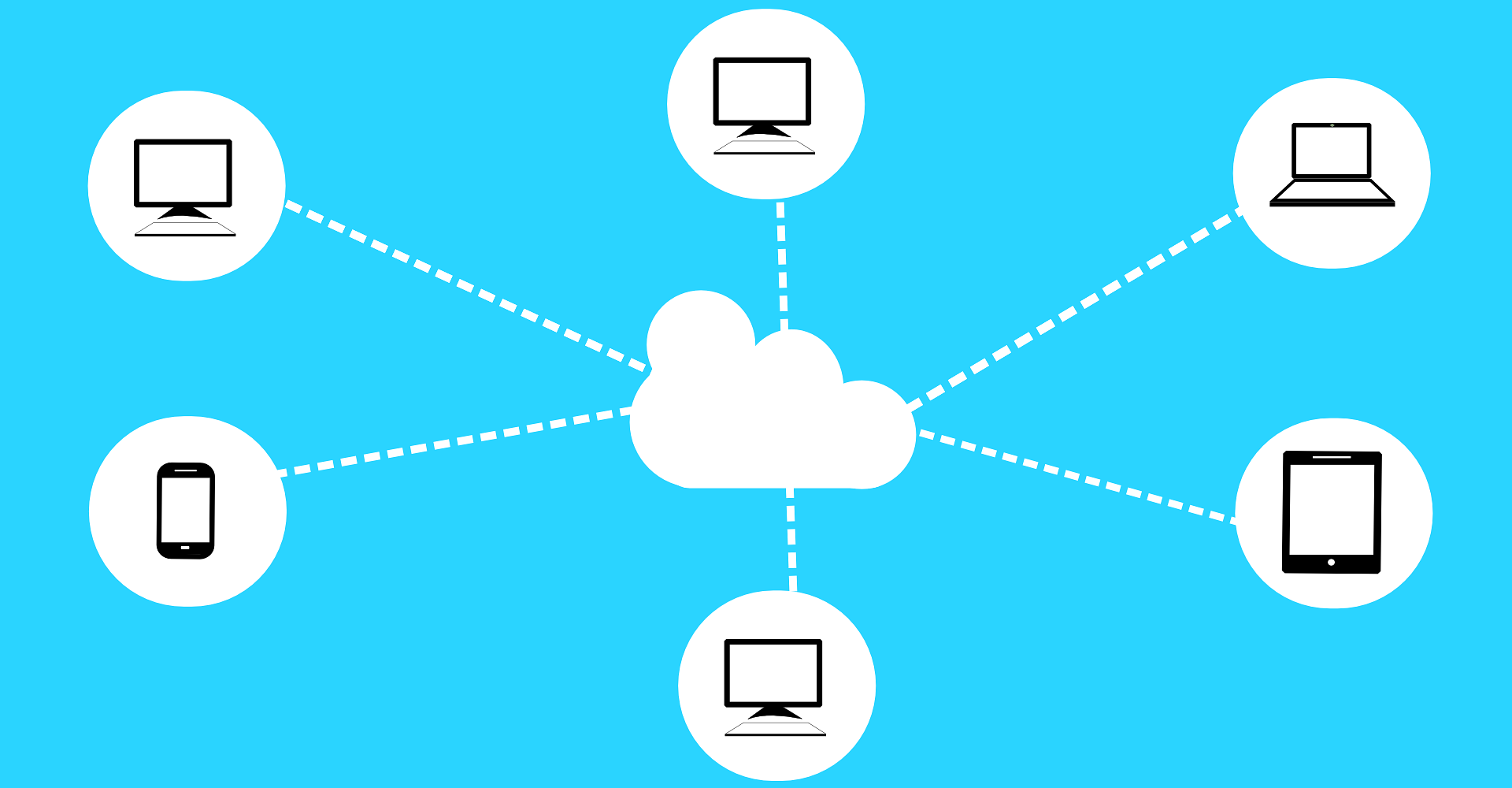ページ内に広告が含まれる場合がございます。
クラウドの利用でまず触れるのが「仮想マシン(VM)」と「ストレージ」です。
オンプレミスでいう物理サーバやローカルディスクに相当し、最も分かりやすくかつ重要な領域です。
本記事では、AWS・Google Cloud・Azureそれぞれの仮想マシン・ストレージサービスを比較し、初学者でも構成しやすいポイントを解説していきます。
仮想マシン(IaaS)の基本比較
各サービスの名称と役割
| 項目 | AWS | Google Cloud | Azure |
|---|---|---|---|
| サービス名 | Amazon EC2 | Compute Engine | Azure Virtual Machines |
| 起動単位 | インスタンス | インスタンス | 仮想マシン |
| UIでの操作性 | 中級者向け(項目が多い) | わかりやすい | GUI中心で初心者にもやさしい |
| 起動時間 | 数十秒〜1分 | 数十秒〜1分 | 数十秒〜1分 |
| OSイメージ | Linux/Windows豊富 | 特にUbuntuに強い | Windows Serverに強み |
構成時の比較ポイント
| 項目 | AWS | Google Cloud | Azure |
|---|---|---|---|
| CPUファミリー | Intel, AMD, Graviton(Arm) | Intel, AMD | Intel, AMD |
| ディスク選択 | EBS(ボリューム型)をアタッチ | 永続ディスクをアタッチ | OSディスク+データディスク構成 |
| 課金単位 | 秒単位(最低1分) | 秒単位 | 秒単位(従量) |
| リージョン/AZ | 世界最多 | 少なめだが高速 | 多くのMS拠点に展開可能 |
オブジェクトストレージの比較
オブジェクトストレージは、VMとは独立して扱える「容量課金型の保存領域」であり、
ログ、画像、バックアップ、アーカイブ等に最適です。
各クラウドの名称と特長
| 項目 | AWS | Google Cloud | Azure |
|---|---|---|---|
| サービス名 | Amazon S3 | Cloud Storage | Azure Blob Storage |
| バケット名称 | Bucket | Bucket | コンテナ(Container) |
| 保存方式 | オブジェクト単位 | 同左 | 同左 |
| アクセス制御 | IAM + バケットポリシー | IAM + Signed URL | IAM + SASトークン |
特徴的な機能
| 項目 | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|
| ライフサイクル管理 | ◎(細かく設定可) | ○ | ○ |
| バージョニング | あり | あり | あり |
| 静的Webホスティング | 可能 | 可能 | 可能 |
| 暗号化 | SSE / KMS対応 | KMS対応 | Azure Key Vault対応 |
VM+ストレージ構成パターン(典型例)
- 単一インスタンス+EBS+S3的構成
-
- EC2+EBS:アプリケーションサーバ
- S3:ログやアップロードファイルの保管
- 複数VM+オブジェクトストレージ共有
-
- Webサーバ群(Auto Scaling)
- バックエンドは全てBlob/S3/GCSで共有・分離
初学者が体験すべき操作
| タスク | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|
| 仮想マシンの立ち上げ | EC2(t2.microなど) | Compute Engine(e2.microなど) | Azure VM(B1sなど) |
| パブリックIPでSSH接続 | ◯ | ◯ | ◯(NSGの許可が必要) |
| ストレージバケット作成 | S3 | Cloud Storage | Blob Storage |
| ファイルアップロード | コンソール or CLI | gcloud CLIあり | Azure CLI or Storage Explorer |
5. VMとストレージに関する注意点
- VM側の注意
-
- パブリックIPはデフォルトで割り当てられない場合がある(GCP、Azure)
- セキュリティグループやFirewallルールの初期設定に注意
- ストレージ側の注意
-
- バケット名はグローバル一意(S3, GCS)
- アクセス制御は「IAM」と「バケットポリシー/ACL」の両面がある
おわりに:クラウドの基礎は「VM+ストレージ」
VMとストレージの組み合わせは、どのクラウドを使っていても必ず基礎となる重要な構成です。
また、将来的にはこの構成を基に「オートスケール」や「可用性設計」へと発展していきます。
次回は、この構成の“裏側”にあるネットワーク設計(VPCやFirewall)について見ていきましょう。