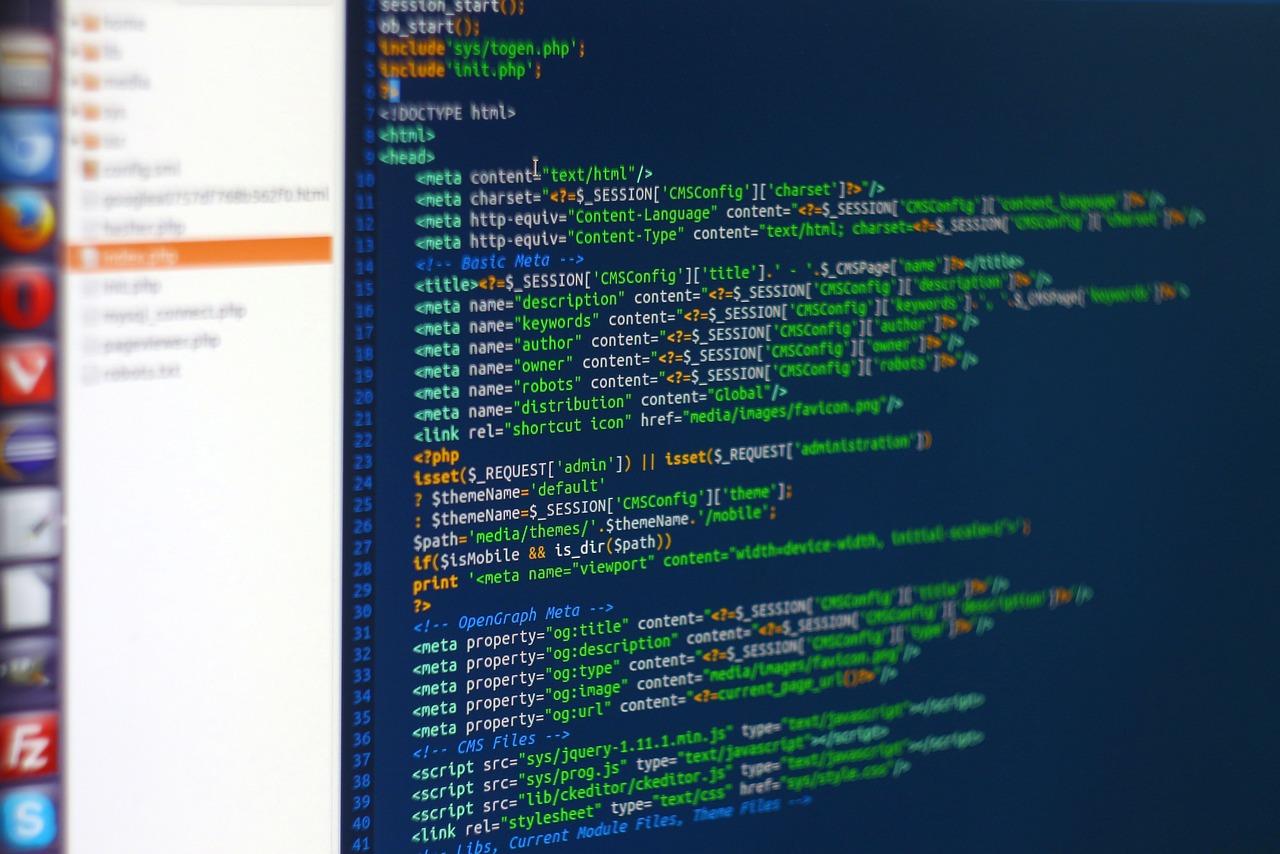ページ内に広告が含まれる場合がございます。
Linuxディストリビューションの中でも、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)は「商用サポート」「安定性」「エンタープライズ対応力」において突出した存在です。
特にSAP、Oracle、金融・公共系の大規模システムでは、RHELの採用実績が多数あります。
本記事では、PreSales視点で「RHELをどんな場面で、どう提案するか」を整理していきます。
HELの基本概要と特徴
RHELは、Red Hat社(現IBM)が提供する法人向け商用Linuxディストリビューションです。
特徴一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商用サポート付き | 年額契約で24時間365日サポートが受けられる |
| 安定性重視 | リリース頻度は控えめ、長期サポート前提の構成 |
| エンタープライズ対応 | SAP, Oracle, VMwareなどの公式認定プラットフォーム |
| SELinux搭載 | 高度なセキュリティポリシー制御が可能 |
| カーネル・パッケージの検証済み提供 | 企業システムでの安定稼働に適する構成 |
→ 信頼性・安定性を最優先とする業務システムに向いています。
サブスクリプションモデルと価格体系
RHELは買い切りではなく、年額のサブスクリプション契約が基本です。
用途や構成によって契約パターンが分かれています。
| サブスク種別 | 用途 | 価格帯(目安) |
|---|---|---|
| RHEL Server(物理) | 単体物理サーバ | 約10~15万円/年 |
| RHEL for Virtual Datacenters | 仮想化ホスト(無制限ゲストOS) | 約40万円/年~ |
| RHEL Workstation | 技術者・設計者用クライアント | 約5万円/年 |
| Smart Management付き | 衝突回避・自動化運用を含む | 上記+α費用 |
※価格は構成や販売パートナーによって変動あり
vSphere基盤での一括仮想化利用には、「Datacenter向けサブスク」を選択するとコスパが良くなります。
RHELを選ぶ理由(ユースケース別)
Oracle DB、SAP HANAなどの基幹系システム
- RHELは公式なサポート対象OSであり、障害時もベンダー連携がスムーズ
- 金融・公共などでは「RHEL指定」の案件も多数
セキュリティ基準が厳しいシステム
- SELinuxによる厳格なアクセス制御が可能
- FIPS準拠やCIS Benchmarkへの対応も◎
長期安定運用が前提の業務
- LTS(10年間サポート)で、中長期運用に安心感あり
- カーネルやミドルウェアのアップデートもRed Hatが検証済みで配布
CentOSの終了とRocky/Alma Linuxの登場
2021年、Red HatはCentOS Linuxの終了を発表し、CentOS Stream(開発寄り)への移行を推奨しました。
この結果、RHEL互換の無償ディストリとして以下が注目されています。
| ディストリ | 特徴 |
|---|---|
| Rocky Linux | CentOS後継としてRHELと完全互換。商用でも急速に採用中 |
| AlmaLinux | CloudLinux社主導。RHELと100%バイナリ互換を宣言 |
| CentOS Stream | RHELよりも先にアップデートが配信される「準開発版」 |
→ 無償でRHEL互換環境を使いたい場合はRocky Linuxが主流です。
PreSalesでの提案ポイント(チェックリスト)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ミドルウェア要件 | OracleやSAPなど、RHEL認定済みが必要か? |
| サポート期間 | 5年 or 10年の運用期間に合ったサブスクリプションを提案 |
| 仮想化構成 | VMware vSphereやKVM基盤上での最適な契約プランを選定 |
| セキュリティ要件 | SELinux、FIPS準拠、脆弱性対応まで含めて説明できるか |
| コスト重視 | RHELが必須でない場合はRockyなどの無償互換OSも候補に |
まとめ:RHELは“信頼性と公式サポート”を重視する選択肢
Red Hat Enterprise Linuxは、「何があっても安定して動き、誰かが責任を持って対応してくれるOS」として、法人ITで強い存在感を持っています。
特に、大規模システム・基幹システム・セキュリティ厳格な業種では、“指定OS”として選ばれることが多いのが現状です。
PreSalesとしては、「なぜ無償Linuxではなく、RHELを選ぶべきなのか」を論理的に説明できることが求められます。