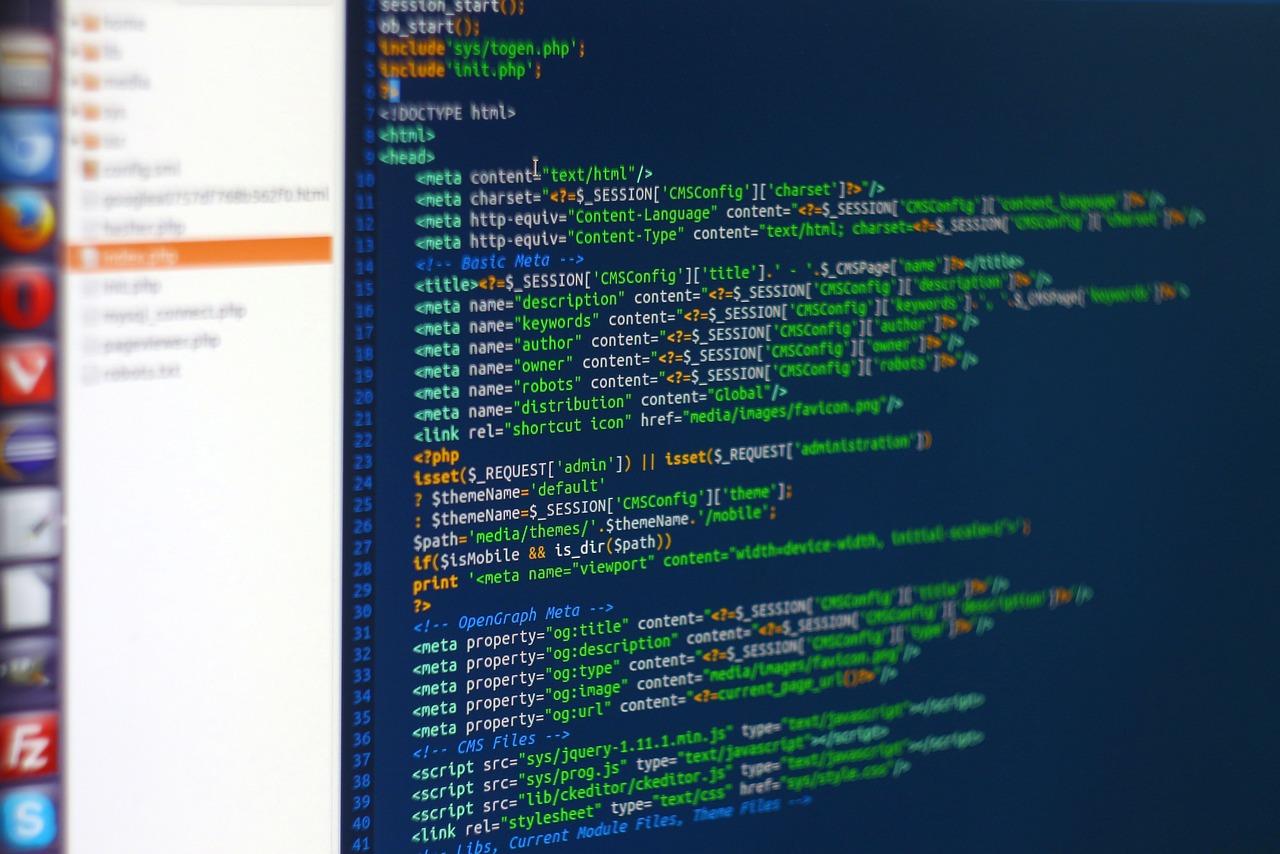ページ内に広告が含まれる場合がございます。
インフラ提案において、OSの「今動くか」だけではなく、「いつまで使えるか」「どこまでサポートされるか」という視点は極めて重要です。
PreSalesとしては、サポート切れによるリスクを未然に防ぎ、計画的な更改・移行提案に繋げることが求められます。
本記事では、代表的なサーバOSのライフサイクル(サポート期間)と支援体制を比較・解説します。
OS別:標準サポートと延長サポートの比較
| OS | 標準サポート期間 | 延長・有償サポート | 合計サポート年数 |
|---|---|---|---|
| Windows Server | 5年(Mainstream) | 5年(Extended Support) | 最大10年+ESU可 |
| RHEL | 5年(Full Support) | 最大5年(Extended Life Phase) | 最大10年+拡張可 |
| Ubuntu LTS | 5年(無償) | Ubuntu Proで+5年(ESM) | 最大10年 |
※上記はLTSまたはEnterprise向けリリースに限定
サポート期間の詳細(バージョン例)
| OS / バージョン | リリース年 | サポート終了 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 | 2013 | 2023(ESU:2026) | 延長サポート終了済。ESUは有償 |
| Windows Server 2019 | 2018 | 2029 | 現在の主力バージョン |
| RHEL 7 | 2014 | 2024(Extended:2026) | EL付きで延命可 |
| RHEL 8 | 2019 | 2029(+拡張可) | 多くの基幹系で採用中 |
| Ubuntu 20.04 LTS | 2020 | 2025(Proで2030) | デフォルトでは5年。延長にはUbuntu Proが必要 |
| Ubuntu 22.04 LTS | 2022 | 2027(Proで2032) | 最新のLTS版 |
PreSalesが確認すべきライフサイクル関連ポイント
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 使用中OSのバージョン | 現在の顧客環境がEOL間近でないか確認 |
| 延長サポートの有無 | EUS, ESU, ESMなど有償オプションの有無 |
| 次期アップグレード方針 | 次に何を使うか?マイグレーション難易度は? |
| LTS / 安定版の有無 | 安定性重視ならLTSまたはフルサポート版推奨 |
| サポート切れのリスク | セキュリティ更新停止、ベンダー未対応などの影響説明が必要 |
サポート終了時の影響と提案トーク例
影響例
- セキュリティパッチが配信されず、脆弱性が放置される
- アプリケーションやミドルウェアの新バージョンが対応しない
- OSバージョン依存のクラウドテンプレートが使用不可になる
提案トーク例
「現在お使いのOSは来年で公式サポートが終了します。以降は脆弱性対応や障害時の保証が受けられなくなるため、計画的に移行をご検討されることをおすすめします。」
→ 「今すぐ入れ替え」ではなく、「1年以内の更改提案」が現実的で受け入れられやすいです。
サポート延長契約・管理製品の活用
| 製品名 | 機能 | 対応OS |
|---|---|---|
| Red Hat Satellite | パッチ配信、構成管理、EUS制御 | RHEL系 |
| Ubuntu Pro + Landscape | LTS延長、サポート管理、構成可視化 | Ubuntu |
| Windows ESU(拡張セキュリティ更新) | サポート切れOSへの有償パッチ提供 | Windows Server |
→ 「予算的にすぐリプレースできない」場合でも、延命+段階的移行を提案できると好印象です。
まとめ:OSのライフサイクルは“提案の起点”
OSのサポート切れは、インフラ更新提案の好機であると同時に、放置すると重大なセキュリティリスクにもつながります。
PreSalesとしては、以下の視点でOSのライフサイクルを評価し、顧客に「なぜ今提案するのか」を納得させる根拠として活用することが求められます。
- バージョン/EOLスケジュールの把握
- 延長サポート可否とコスト感
- マイグレーションの実現性と必要期間